皆さん、こんにちは(^.^)
5つの気の作用続いています。
前回はこちら

5つの気の作用(3)
皆さん、こんにちは(^。-) 先週 の続きです。 (3)外邪から体を護る防御作用 「防御」とは読んで字のごとくですが、 体表において、外邪の侵入を防御する働きです。 例えば、「衛気(えき)」という種類の気は、体表をバリアーの...
(4)体液や内臓をあるべき場所に保持する固摂作用(こせつさよう)
気の固摂作用とは、体にとって必要なものを、
あるべき場所にしっかり保持することをいいます。
血が脈外に出ないように、精が漏れないようにするなど、
本来あるべき場所から必要なものが失われないようにする他、
発汗調節や尿量調節も行います。
人間の体には、血液・汗・大便・小便・唾液・精液・帯下(おりもの)……など、
様々な体液があります。
例えば、血液は血管の中にちゃんと流れ、 血管の外へ漏れ出ないようにしなければなりません。
打った覚えもないのに内出血を起こしていたり、鼻血がよくでる、
歯ぐきからの出血、尿漏れや、暑くもないのにやたらに汗が出たり、
常に涙が溢れてきたりと、
これらは、固摂作用の失調と言えます。
乳幼児のよだれ、小児のおねしょなどは、固摂作用がまだ未熟のために起こります。
また、内臓もあるべき場所は決まっています。
重力に抗して内臓の位置が保たれているのは、
気の固摂作用があるためです。
固摂作用が失調すれば、胃下垂、子宮脱、あるいは脱肛などがおこり、
加えて、胎児も固摂の対象のひとつです。
結構、身近なちょっとした症状に、
固摂作用の失調が関わっていることがうかがわれますね
自分の症状に照らし合わせて、
なんとなく原因がわかるとちょっと気持ちが楽になりますよね。
今日も一日すべての事柄に感恩報謝です。(^_-)



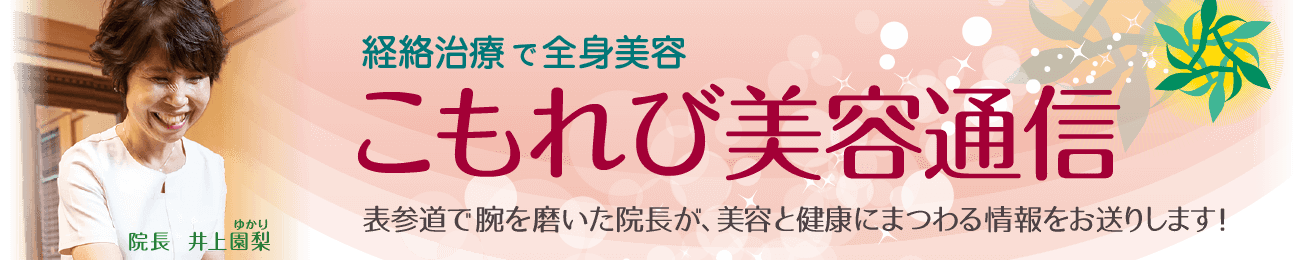
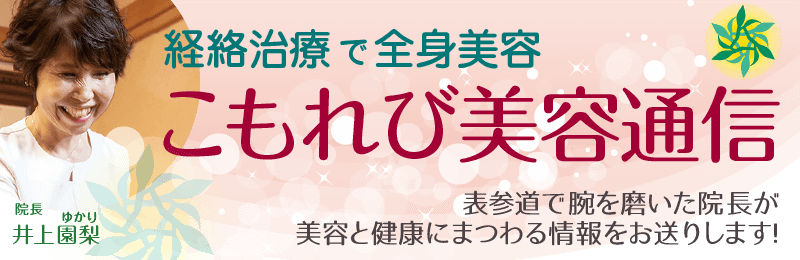


 Facebook
Facebook Twitter
Twitter Instagram
Instagram
コメント一覧